作品のコンセプト:怪異は現象と解釈で成立する
以前、別の本の紹介でも書きましたが、事件を推理するのは、なにも探偵の専売特許とは限りません。
科学者だって、世界の真理(謎)を解き明かします。
ついでに、人が起こした事件の謎も解明します。
そして、本作では、民俗学者で若き准教授の高槻彰良が、怪異の謎と、人が起こす事件の真相を解明します。
探偵の相棒役は、大学一年生の深町尚哉です。
1作目『民俗学かく語りき』の背表紙の説明を読むと「凹凸コンビが怪異や都市伝説の謎を解釈する」と書かれていました。
彰良が身長181センチで、尚哉が身長172センチのようなので、凹凸コンビとは身長差もかけているのかもしれません。
題名には、「推察」という言葉が使用され、怪異の謎は「解釈」するという表現を使っています。
どちらの表現も、人が引き起こす事件の前に、「怪異」が起こったいきさつを物語るのがメインになっているため、使われている言葉になります。
彰良の高説によると、怪異は「現象」と「解釈」で成り立っています。
そもそも人は己が信じたいものを信じ、都合の悪い真実からは目を背け、蓋をし、なかったものにする生き物です。
何かの現象が起こった時、人はまず、科学的に説明のできる可能性について考えます。
ですが、すべての可能性を当てはめても説明がつかなかった場合、人はその現象を「怪異現象」として認識します。
科学が存在しなかった時代は、今よりももっと些細なことが怪異現象となっていました。
弱い人の心が、説明のつかない事象について恐れを感じ、怪異を怪異たらしめ、お化けを生み出していくのです。
そして怪異現象には必ず、「解釈」が存在します。
現象のまま放っておくことができない人が、怖いものを怖いままにできず、そこに物語を作って与えます。
それが「解釈」です。
説明のつかない事態を、人は恐れるのです。
解釈をすることで、自分の理解できる範疇にある現象なのだと思い込もうとする。
それが現実にあり得ない説明だったとしても、全く何もないよりは、いくらかましだからです。
だから彰良は言います。
大事なのは、現象に対して、どんな解釈をするのかだと。
怪異現象を誰かが解釈する場合は、たいてい、現象そのものを歪める可能性が高いのです。
だから、解釈をするときは、気を付けないといけないと。
不思議な話が生まれるのは、実際に起こった事件が陰惨すぎるからなのです。
事件が惨ければ惨いほど、人は真実を隠そうとする。
そして、別の真実:神がかり的な事象や、化け物が起こした事象として都合よくとらえられる真実を用意します。
嫌な事件は、伝説や物語に置き換えればいい。
そうすることで人は安心を確保できるのです。
現実だと思うと辛すぎることでも、虚構の世界のことなら耐えられます。
そして、その奥に隠された真実に目を向けないように仕向けるのです。
だから彰良は生じている事象についてまず「解釈」を理解し、その「解釈」に至った真実を「推察」するのです。
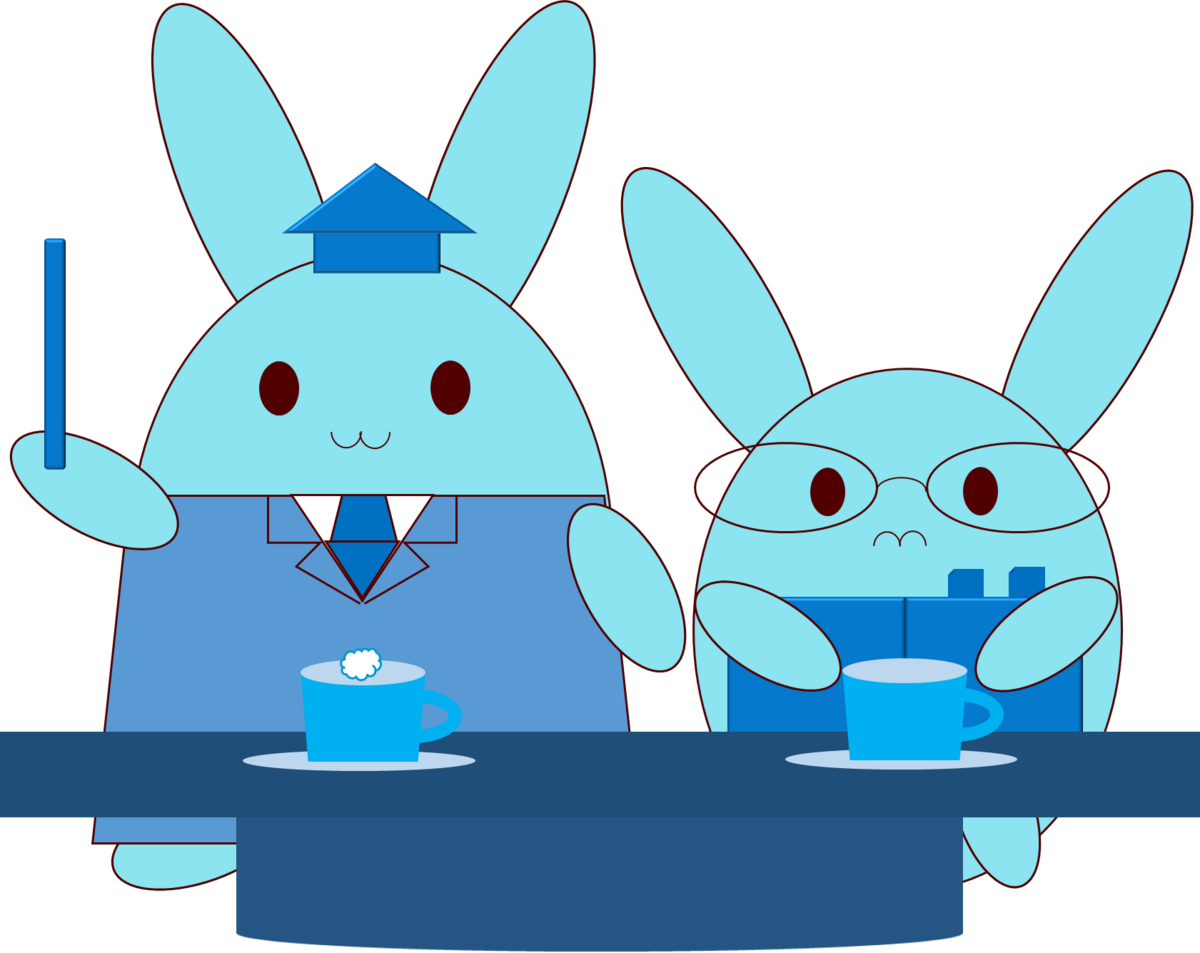
彰良がやろうとしていることを、まとめてみたんですが、1カ所にまとめると、長くて難しくて、わかり辛い文章となってしまいました。
ですが、大丈夫です。
始めの1巻と2巻で、発生した現象のエピソードを経験しながら、徐々に、このコンセプトに書いた内容の一端が登場してきます。
よって、読者はゆっくり、彰良の考えを浸透させることができます。
彰良は大学の先生ですから、ゆっくり、丁寧に、少しずつ、尚哉が理解できるように説明していきます。
重要なことは尚哉が繰り返し、自分に言い聞かせながら、読者にも教えてくれます。
尚哉が悟ったようにつぶやく心の声を、拾いながら読むことをお勧めします。
民俗学かく語りき 冒頭7ページまでの感想
本作の語り部である尚哉は、10歳の夏休み、ある奇妙な体験をしました。
それは現実にはあり得ない世界(異世界)に迷い込むというものでした。
そのせいで、尚哉の耳は、人の嘘を声の歪みとして知覚してしまうという特殊な能力を持つことになってしまったのです。
そして、この能力を持ってしまったがために、尚哉は不遇で寂しい人生を歩むことになりました。
この尚哉の身に起こった出来事は、1冊目の冒頭で紹介されています。
初めて本作を手に取って冒頭を読んだ瞬間に思ったことは、
話が凝っている!
という一言につきます。
何かモデルとなる神話や逸話が存在するのかどうかはわかりませんが、これまで読んできた怪異現象を扱っている物語の中でも、ダントツの逸品だと思います。
冒頭だけでも、ザワザワとした気分になりました。
私の個人的な見解ですが、
当時、尚哉は高熱を出していたとのことだったので、おそらく、、生死を彷徨う状態に近いくらいの熱を出していたのではないかと思われます。
だからこそ異世界に迷い込むことができたのではないかと思うのです。
そして異世界の門を開ける通行証が、「お面」だったのではないかと思います。

それともう一つ、やはり個人的な見解ですが、
尚哉自体に、何かマイノリティ的な特殊性があった可能性が高いということです。
同じ条件がそろった誰もが行ける場所ではなかったのではないか?とも思われるからです。
異世界に迷い込んだ尚哉が、元の世界に戻って来るためには、とある代償を払わなければならなくなりました。
代償には、選択肢が3つあったんです。
1つ目と2つ目の選択肢は、そのまま言葉のとおりだったと仮定するならば、おそらく、自分に備わっている当たり前の能力が1つ失われる。
という意味だったのでしょう。
だから子供だった尚哉は、「それは大変なことになる」と思ったのに違いありません。
3つ目の選択肢は、ちゃんとした意味が当時は分からなかったのと、1つ目と2つ目に比べれば大したことはないという誤った判断に誘導されてしまった結果、選ばされた選択肢だったのではないかと思うのです。
しかも、3つ目の選択肢を選んだ結果、尚哉は、人間には到底持ちえない、特殊な能力を持つことになりました。
つまり、1つ目と2つ目の選択肢は、能力が失われるというもので、3つ目の選択肢だけは、神のごとき能力が授かるというものだったのです。
そしてそれは尚哉の祖父が、尚哉に選ばせた選択肢であり、尚哉を唯一守ることができる選択肢でもあったのではないかと思われるのです。

どれを選んでも、結果は同じだったのかもしれません。
ですが、人はとかく、選ばなかった選択肢が気になるものです。
そして永遠に、選ばなかった道を模索して後悔し続けるものです。
どの選択肢を選んでも、後悔は永遠にするものなのに、尚哉がそれに気づくのにはもっと長い時間がかかるように思います。
それから、個人的な見解をもう一つ加えます。
高熱を出した尚哉は、おそらく、一度死んでしまった可能性も、あるのかもしれないということです。
死んでもいないのに行ける世界ではないような気もするのです。
なぜか、死んでしまった孫を生き返らせるために、祖父が手助けをした可能性もあるのではないか?とも思われるのです。
そんなふうに推察していくと、「代償」の意味が少し違ってくる可能性もあります。
そして3つの選択肢は、予定していなかった「死」を取り消すための手段だった可能性もあります。
3つの選択肢が、死んだはずの人間を生き返らせるための儀式だったのだとしたら、「代償」を払うのは当然とも言えるわけです。
もう少し先の巻になると、尚哉が体験したモノの正体が、一旦はわかります。
尚哉は一人では何もできなかったことでしょう。
彰良と出会ったからこそ、一歩前に進む勇気を持ちました。
ピンチだって、二人が一緒に居れば、乗る超えることができるのです。
これから始まる二人の冒険をぜひ楽しんでみてください。