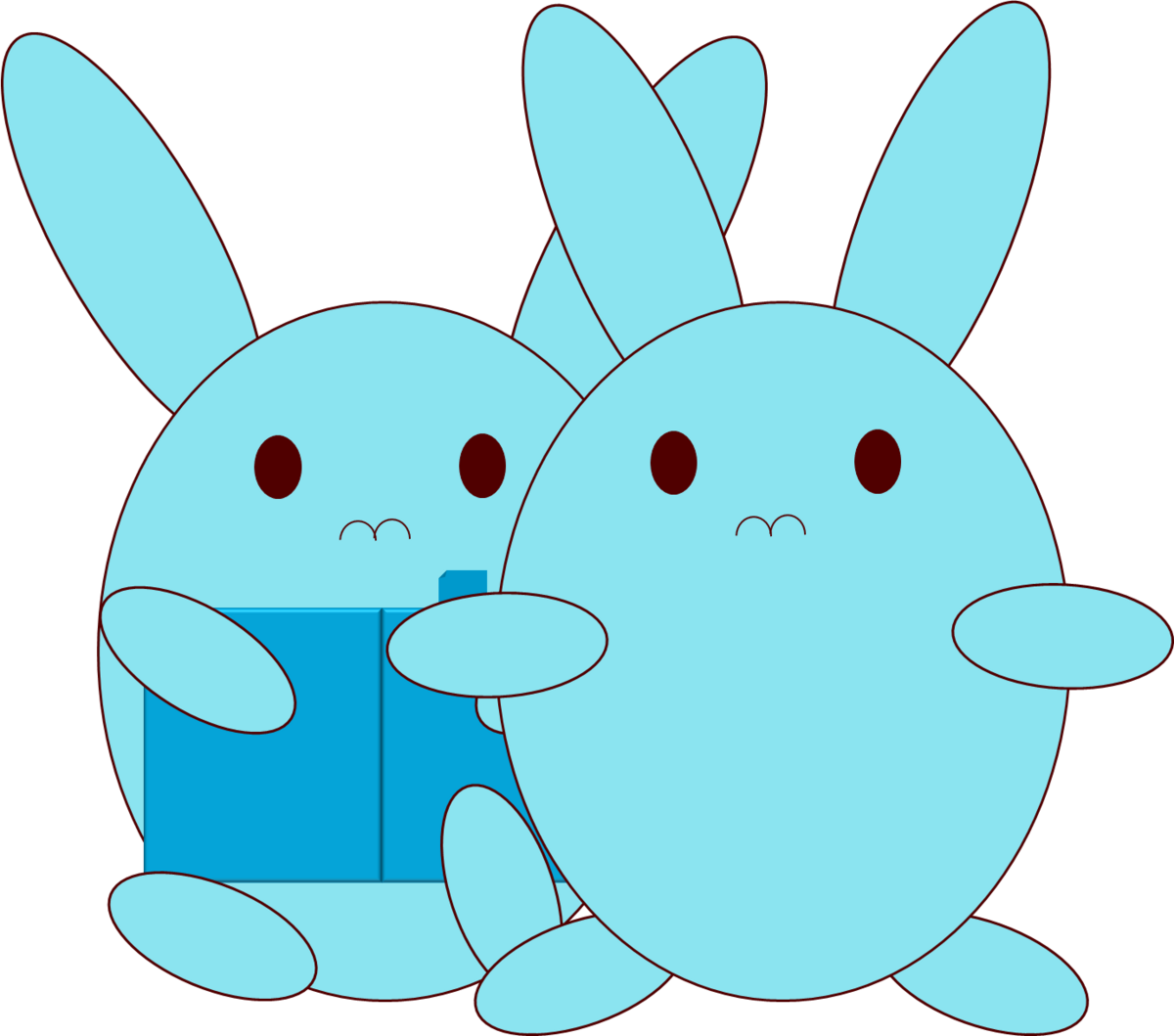呪いは矛盾したシステム
怪異とは、実際に生じている「現象」と、ちょうど都合よく存在する「解釈」によって成立します。
以前のブログでもご紹介しました。
そしてこの理論は、本作の主人公:高槻彰良准教授が掲げる根本理念でもあります。
「呪い」も基本的には怪異と同様の捉え方となるようです。
呪いとは、実際に生じている「災い」と、タイムリーに存在した「原因」によって成立するシステムです。
人は何か悪いことが起こった時、原因は何かと考えます。
特に日本人は、根本原因を調査して、改善しようと努める意識が高い民族だと個人的には思います。
ですが、常識的に考えても、科学的に考えても、説明のできない現象というのは存在します。
しかし、人というものはとかく理由が必要な生き物でもあります。
例えば、誰かを好きになるときには理由なんて必要なかったとしても、別れる時には必ず理由が必要になります。
理由もなく別れたいと言っても、相手は納得してくれませんからね。
仕事を辞める時だって、ただ辞めたいと言っても、そう簡単に会社を辞められるわけでもありません。
嘘でも何でも、相手が納得するだけの説得材料が必要となります。
つまり、人はですね、プラスのことに対しては、理由があってもなくても大丈夫な生き物なのですが、マイナスなことに関しては、必ずその理由が必要となる生き物なのです。
よって、何か悪いことが起こり、どうしてなのかをあれこれと考え、どうしても説明がつかない場合は、逆に、何かこれに匹敵する原因が最近なかったかなと、探し始めるわけです。
そして都合よく、結びつきそうな原因を見つけて紐づける作業が「呪い」というシステムになるわけです。
呪いは、誰か(呪われた本人、もしくは周りで状況を知っている人)が、原因を災いの理由として認定することで、初めて成立するものなのです。
「呪い」という言葉は便利な言葉です。
理由とが原因とか、全く思い当たる何かが存在しなかったとしても、ただ漠然と、「これは呪いだね」と言ってしまえば、それで事足ります。
「呪い」という表現だけで、何もかも完結してしまいますから。

昔は、原因となるもの(藁人形・不幸の手紙・御札)が具体的にあって、わかりやすい時代もあったかもしれません。
ですが、現代ではなかなか、原因となる迷信的なものが少なくなってきましたから、むしろ、何も理由や原因がない場合にこそ、「何かの呪い」という便利な一言で片づけてしまうパターンもあるように思います。
一旦整理します。
「呪い」というシステムは、災いが起こった後に、その理由や原因を特定するために行われる紐づけ作業です。
災いが起こった後に、「これは何かの呪いだよね」っていう話になります。
そして、この瞬間に「呪い」が発動されます。
もちろん、普段の生活で、災いらしきことが起きない限りは、「呪い」という言葉を思い出すことはありません。
皆さんは、この矛盾に気付きましたか?
時間軸がおかしいということに気付きましたか?
誰かや何かに「呪われる」から災いは起こるものなのに、、
災いが起こらなければ「呪い」が発生しないという矛盾に。
もともと存在していなかった「呪い」を、「災い」が起こった後に、発生させるなんてことは、不可能だということに。
つまり、日本人が言う「呪い」とは、発生させるのが不可能な現象でもあるのです。
ここまで読んでいただいてありがとうございます。
何を言っているのか!と、頭を悩ませた方も多いでしょう。
でも大丈夫です。
本巻を最初から最後まで読破すれば、どういうことなのか、ジワジワわかってきます。
実感できます。
本巻のテーマは「呪い」でしたが、
彰良が本当の意味で尚哉に伝えたかったことは、「呪い」ではなかったのです。
題名を良く見ると、わかります。
存在するはずのない呪いの先にある彰良の想いを、尚哉がちゃんと受け取れるかどうか、ぜひ、確かめてみてください。
准教授・高槻彰良の推察3 呪いと祝いの語りごと
第1章 不幸の手紙と呪いの暗号(2本仕立てになっています)
1本目は、尚哉の友人予備軍:難波要一が、不幸の手紙で呪われるというエピソードです。
そしてこのエピソードは第2章まで続きます。
難波は、尚哉でも友人になれるかもしれない青年です。
根がいい奴なのです。
あまり嘘を言いません。
嘘を言う場合は、何か事情がある時だけです。
少なくとも難波自身のメリットのために嘘をつくようなことはなさそうです。
彰良と出会ったことで意識が変化してきた尚哉ですが、最後のとどめを刺して、友人になってくれるのはきっと、難波になるのだと、読者も彰良も確信しています。
不幸の手紙は、私も小学5年生の時に届いたことがありました。
郵便で届いたんですが、切手を貼らずに誰かが投函した手紙でした。
郵便配達の方が、切手代を払って受け取るか、受け取りを拒否するかと聞いてくれたんですが、中身が、不幸の手紙かどうかなんてわかりませんでしたし、昔は今ほど警戒しなければならない世の中でもなかったので、切手代を払って受け取ってしまいました。
受け取らなければ良かったと、とても後悔しました。
なにせ初めて受け取ったので、どうしていいのかわからないし、恥ずかしくて誰にも相談できなかったんです。
両親は共働きで家にいなかったので、相談する時間もなかったのですが。
怖くて一人で、泣きながら悩んだんですが、結局、誰かに手紙を書いて投函することはできませんでした。
もちろん、何の不幸も起こりませんでしたが、手紙が来たこと自体が不幸だったので、無傷とは言えませんよね。
人間不信になりかけましたしね。
大人が知らないところで、子供たちが傷つく遊びが流行るのは、哀しいことです。
お子さんやお孫さんがいる方は、念のため、不幸の手紙もしくは、それに匹敵するSNSのメッセージなどに悩まされてないかどうか、確かめてあげてください。
2本目は、とてもドラマチックな呪いの暗号を解くエピソードでした。
高校生の淡い恋物語でした。
あまり書いてしまうと、読んでない方に申し訳ないのですが、、
結構、感動しますので、周りに人がいない場所で読んだ方がいいでしょう。
図書館が大好きな女子高生が、図書館ならではのゲームを行います。
私も図書館が大好きなので、何かのゲームをしてみたいなという憧れはありますが、、本自体に何かを書き込んだり、故意に傷つけるという行為は、私には無理ですね。。
でも、中高生の頃は、机とかロッカーとか、トイレの個室の中とかに、好きな人の名前を書いたりするなんて経験は、誰しも1回くらいはあるのではないでしょうか。
私は小心者なので、誰にも見られないように、家オンリーで使用する消しゴムに書いたりしてましたが。
そういったことの延長にあるエピソードだったのかなと思います。
恋とか愛は、形のないものですから、どこかに軌跡を残したくなるものなのかもしれません。
第2章 鬼を祀る家
高槻ゼミの筆頭院生:生方瑠衣子の実家のペンションに、彰良と尚哉と健司が遊びに行くというエピソードです。
瑠衣子は美人で家庭的な女性なんですよね。
彰良という絶対的な存在に出会ってしまったわけですから、他の男性に心を奪われることもなさそうな感じがしますし、かと言って、彰良が誰かと結婚する感じもしないので、このまま2人は独身のまま、研究者として一緒に生きていくような気もします。
ちょっと残念です。
彰良と尚哉と健司は翌日、鬼伝説がある洞窟へ出かけていきます。
日本各地に散らばる鬼伝説の真実がどういうものなのか、民俗学的な勉強をすることになりました。
現代では、鬼なんて存在しない生き物だと、誰しも知っています。
だとしたら、昔昔の話に登場する鬼だって、鬼ではなかったのです。
鬼でないなら、一体何だったのでしょうか。
人と会話ができる生き物なのだから、やっぱり人だったと推察するのが妥当なところでしょう。
では鬼退治とは、どういう意味になるのか。
そこには、惨い悲劇があったと考えるのが正解でしょう。
だからこそ、昔話として親しまれ、真実は闇に葬られたのだと思われます。
現代ではあり得ないし、許されない所業です。
そういった鬼伝説の歴史を背負って、生き続けてきた鬼頭家の人たちを、彰良が呪縛から解き放ちます。
毎回思うのですが、怪異を悪用せざるを得なかった人たちに対して、彰良はとても優しく裁きを行います。
彰良に裁かれたとしても、その後は、みんな、幸せになれるような気がするんです。
幸せになるために、真実を追い求める彰良が、どこまでも眩しくて素敵なんですよね。
だからでしょうか。
彰良の真実が明らかになった時、彰良がどうなってしまうのかと、少し心配な気分にもなります。
【extra】それはかつての日の話(巻末収録)
健司が主人公のエピソードです。
健司が彰良と出会ったのは、小学1年生の春。
通う学校も違い、住む世界も違う二人が、これまでずっと支え合って生きてきたのは不思議なことです。
健司もそのことは実感しています。
特別なことは何もなく、普通に出会って、普通に友達になって、なぜかずっと一緒にいる二人の最初の物語であり、初めての怪異体験でもありました。
肝心の彰良は霊感が1ミリもないのに、健司にはちょっとばかり霊感があるのかもしれません。
健司はたぶん、見たことがあるから、幽霊が怖いのでしょう。
彰良は見たことがないから、見たがるのだと思います。
人間に対してなら怖いものなしの健司ですが、別の一面を見ることができました。
そして健司は最初っから、健司なんだなと思いました。
正義感が強くて彰良思いのちょっと可愛い健司を堪能できるエピソードでした。